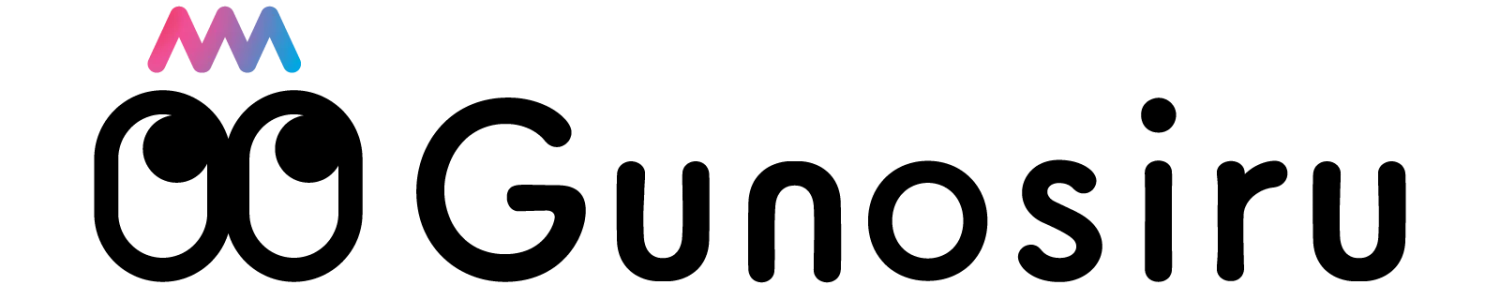こんにちは、採用広報の市村です。今回のGunosiruでは、広告テクノロジー企業の相関図を示したLUMAscape日本版「カオスマップ」の作成者である近藤さんにインタビューしました。いまGunosyで注力されている動画広告の話や、現在のインターネット広告業界の流れ、今後業界に訪れるであろう未来について、近藤さんの見解を伺いました。ぜひご覧ください。

■近藤さんプロフィール
2001年~株式会社セプテーニ/アドネットワーク部の設立、国内外アドネットワークのメディアバイ、プランニング、コンサルティングを統括し、自社アドネットワーク「Spider!」の商品企画から販売まで行う
2011年~広告テクノロジー企業の相関図を示したLUMAscapeの公式ローカライズ版「カオスマップ」の作成をスタート※今後も更新予定
2012年~イーグルアイ設立(代表)※セプテーニ連結子会社
2014年~株式会社セプテーニ/Japan Display Advertising Summitの主催
2015年~xAd(現GroundTruth)※日本法人の営業責任者
2017年10月~Gunosyに参画
いま必要な「嫌われない広告」
-Gunosy入社前のご経歴を簡単に教えてください
私はセプテーニグループの新卒の内定者として2000年秋頃からインターンを始めて、そこから約16年ほどセプテーニグループでデジタル広告に携わり、その後、xAdという米国アドテク企業の日本法人の立上げを行いました。参画した理由は、セプテーニ時代に行った子会社立上げの経験を活かせると考えたのと、純粋に外資系企業の日本法人創業ということに興味があったからです。xAdでは、営業責任者として、位置情報テクノロジーを活用した広告商品*1を、様々な大手ナショナルクライアントに裸一貫で乗り込んで提案していました。その位置情報テクノロジーというのは米国では非常に有名で、当時日本にもその流れがきていたこともあり、多くのクライアントに実装していただくことができました。
-インターネット広告業界に長く身を置かれている近藤さんですが、当時どのように広告を捉えていたのでしょうか?
当時といいますか、ここ数年は広告が嫌われものになってきているなと考えています。P&Gさんが訴え業界に大きな影響を与えたブランドセーフティ問題もありましたし、広告はブロックされるものになってきていて、「本来それって広告なんだろうか?」と思う訳です。じゃあ、ユーザーに嫌われない広告ってなんだろう、ユーザーが嫌がらない広告を出していきたいと、特に前職の頃からはそこを意識するようになりました。たとえば位置情報テクノロジーでは、とある衣料品店を訪れたユーザーに対し、類似した他の衣料品店の広告を配信することができますが、ユーザーにとってノイズになってしまう可能性もあります。なので、そこは「ユーザーに嫌われない広告」ということをとにかく意識して設計していました。
ブランドセーフティ/「広告が適切なWebサイトやコンテンツに表示されているか?」
ポルノコンテンツや反社会的活動関連など、そこに広告を掲載することでクライアント(広告主)のブランドイメージを大きく毀損してしまう可能性があるWebサイトやコンテンツに対して、そういったページへの広告掲載をいかになくしていくか、ということがブランドセーフティの考え方。現在のインターネット広告はそのほとんどが「運用型」のため、広告主が自社の広告がどのようなコンテンツに表示されているかを把握することが困難であることが、この問題の発生に起因している。
Gunosyとのクロスポイント
-Gunosyに興味を持った理由は?
Gunosyのことはもちろん知っていましたし、CRO長島とも面識がありました。実は、xAdの位置情報テクノロジーをGunosyで実装して欲しかったんです。長島とランチする機会があってそんな話をしていたら、「じゃあGunosyで近藤さんがやればいいのでは?」とご提案いただいたんです。さらに、「Gunosyがやろうとしていることと、方向性がずれていないのであれば、xAd以外のベンダーも含めて検討していい」とも言っていただけました。それが入社を考えたきっかけですね。
-「グノシー」に対してどのような印象をお持ちでしたか?
GoogleやYahoo!JAPAN、LINEではないものの、きちんとボリュームのある一つのメディアになってきているという印象でした。全て自社内で完結できてしまっている現状に加えて、今後さらに外部の仕組みと連携することで、よりレベニュー*2に貢献できるのではないかと考えました。あとは、「グノシーってこうだよね」というメディアとしてのブランドを、自分の強みを活かして変化させていきたいという思いがありました。たとえば、あるメディアに常に出てくる広告が外資系ブランドなのか、或いは全く聞いたことのない何かの商品なのかでは、そのメディアの印象は随分と変わってきますよね。直接ナショナルクライアントに営業に行って、クロージングまで出来ることが私の強みなので、そういったクライアントを開拓し、「グノシー」の新たなブランドイメージに寄与することができるのでは、と考えました。
-入社の決め手は?
一言でいうと、自分自身の「野心」ですね。メディアとしての立ち位置がきちんとあって、さらにそこに自分が貢献できそうだと思いました。私は「グノシー」というメディアをよく理解した上で、ここに加わったときが自分が最も活躍できる範囲が広く、且つ会社全体に与えるインパクトが大きいだろうと思いました。Gunosyでやりたいことや、できるであろうことがどんどん浮かんできて、自分の得意領域で必ず実績を残し、その後は一部署に留まらず、様々な部署の仕事やミッションにも関わっていきたいと考えました。なので、今は自分のミッションに対して100~120%以上の成果を出し、いずれは社内の他の事業にも関与していけたらいいなと思っています。
Gunosyは自ら流行りやトレンドをつくりだせる環境
-入社後、Gunosyはどのような印象ですか?
まず、圧倒的に良い文化だと思うことが二つあります。一つ目は「数字は神より正しい*3」という考え方です。毎日、朝会で昨日の数字や計画の進捗を管理、共有する文化は素晴らしくて、続けていくべきだと思います。二つ目はSlackでのオープンコミュニティーで、メンバー含めた全社員が役員たちと直接話せることです。何かのプロジェクトについて、役員に対してメンバーが気軽に意見したりリアクションしたりできて、非常に風通しが良いと思います。大きな組織においては、社長や役員等の意思決定者や事業責任者とメンバーの間で、一貫した意思疎通ができていないケースが往々にしてありますが、それでは良いパフォーマンスは生まれません。実際に私たちは、それが体現できていて、今後も担保していこうという意志もある。そこはすごくいい文化だと思いますね。
-どのような人がフィットすると思いますか?
自分で流行りやトレンドを生み出していきたいという人は親和性が高いのではないでしょうか。Gunosyでは、新規企画を起案してから着手するまで本当にタイムラグがないので、自分自身で起業を考えている人でも、Gunosyのアセットを利用してそのやりたいことに取り組むほうが良いと思える環境です。その方がスピードも速く、世の中に与えるインパクトも大きいはずです。たとえば今年の2月からスタートしたグノシー内でのライブ動画コンテンツも、昨年の夏くらいに米国での流行りを基に企画立案されて、10月には予算固め、2月にはローンチというスピード感で生まれたものでした。
他社がやらないこと、できないことをやる
-その新しくスタートしたライブ動画コンテンツは、どのような形で広告と関わるのでしょうか
ライブ動画コンテンツの一つ、ユーザー参加型のクイズ番組「グノシーQ」にて、クライアントにスポンサードしていただき一つの番組を作っています。既に出稿実績もありますし、それは非常に理想的な状態で実現できたと思っています。ユーザーは20分程「グノシー」内にてライブクイズに参加していて、番組内で簡単な商品紹介動画が流れたり、クイズの設問に商品が出てきたりするのですが、ユーザーが「この広告嫌だな」と感じる過度のコミニュケーションにはなっていません。そこに最もこだわって設計しました。ある程度のヘイトはあるかもしれませんが、「広告」が、一個のクイズ番組の中できちんとひとつの要素になっていて、基本的にはポジティブになるであろうというバランスになっています。クライアント満足度を考えたときにも、こういった番組をクライアントと「一緒に作っていく」こと自体が、良い影響を与えていると感じます。ただし定型的な広告商品ではなく、クライアントごとにストーリーやクリエイティブを考えて提案しなければならないので簡単にできる訳ではありませんが、非常に新鮮で面白い取り組みですね。
-近藤さんがそういった新規の広告商品を企画されるときに考えていることは?
前提として、私たちのチームでは、主に新規の広告商品企画・立案、 商品開発にかかる市場調査、外部パートナーとの連携をタスクとし、営業チーム全体のセールス拡大に寄与できるアクションをミッションとしています。そこで新規の広告商品を企画する上で私が常に意識しているのは、どう他社と違いを出すか?ということです。なぜかというと、「グノシー」よりもリーチやユーザ数の多いメディアもあり、彼らと同じ広告商品で勝負をしても勝てない。だから、彼らができないことや、やらないことをやる。この商品は他社でもできるだろうか?ということを必ず真っ先に考えますね。

ルールを守らない企業は淘汰されていく
-今インターネット広告業界にはどのような風潮があるのでしょうか?
広告商品でいえば、今インターネット広告は全体的に運用型に流れていて、Gunosyでも広告売上の6~7割が運用型で、世の中の動きと同様です。今後もこれは変わることはありません。また業界全体としては、これが最も適切な表現だと感じますが、「きちんとしなければならない」という風潮があると思います。前述したブランドセーフティの問題や、クリエイティブの表現方法、ビューアビリティの向上にアドフラウド対策等、きちんとルールを守らなければ、業界につまはじきにされるでしょう。さらに、個人をターゲティングするような表現や、広告の仕組みが段々とやりづらくなってくると思います。最近では米Facebookの情報流出問題も記憶に新しく、その影響は遅かれ早かれどのインターネット広告企業にもやってくるはずです。上場企業だからルールを守る、未上場だから守らなくても問題ない、ということではなく、一つのメディアとしてそのようなユーザー保護の流れをきちんと汲んでいかなければなりません。業界が健全でないと判断されれば、良い人材も流入してこなくなってしまいますから、その点でも危機意識をもつべきでしょう。さらにデバイスの観点でいえば、全体的にスマートフォン以外の次の一手が全く打てていないので、そこで何を考えて、どう新しい波をつくるかが重要になってくるかと思います。
ビューアビリティ/「広告が実際に閲覧可能な状態で表示されているか」
配信インプレッション全体のうち、「実際にユーザーがその広告を閲覧可能な状態にあったインプレッション」が占める比率のこと。Webサイトの広告枠は、画面を下部までスクロールしないと見られないような掲載枠が多く、多くのユーザーは、スクロールしてその掲載枠が画面に出現する前に、そのページ自体を離脱しているため実際には見られていないケースが多い。それでも広告主はそれらの「実際には表示されていない」広告にも課金させられているということが問題となっている。
アドフラウド/「広告がbot(機械)ではなく人に表示されているか」
不当に広告表示回数等を水増しするためにされた、人ではなくbotによる広告閲覧やクリックのこと。
業界は今後人材育成に本気で取り組むべき
-今後のインターネット広告業界に求められることは何でしょうか?
業界全体で、人材育成に本気で取り組むべきだと思います。新卒含め若者を採用している各企業は、来てくれる彼らの力をどう底上げしていくかを考えるべきです。芽が出た人だけが育っていくのではなく、私たち自身が、彼らの成長をどう後押しできるか考えるべきという意味です。市場を成長させるためには、人の成長が一番で、それがないと市場の成長は鈍化してしまいます。私もアドテックなどのイベントに登壇させていただく機会は多くありますが、次世代を担う若手がもっと前に出ていける環境を作らなければと思いますね。逆に、この業界にいる、あるいは今後入ってくる若い人たちに私が求めるのは、「広告に対して好奇心を持つこと」でしょうか。ただこれは持とうと思ってもてるものではないので、難しい問題ですね(笑)。私は昔から、業務時間を多少削ってもいいからとにかくドラマや映画を見るように自分の部下には伝えています。ドラマでは合間のCMや伝えたいメッセージで旬なトレンドを知ることができ、それが広告にも繋がってきます。映画も、何十億もの製作費が一体何にかかっているのか等、興味をもって自分で考えてほしいですね。映像技術の発展やトレンドを知ることは、クリエイティブでメッセージを伝える仕事に携わる人間として、非常に重要です。とにかく様々なことに好奇心をもって日々生活してほしいですし、そういった人たちが業界の未来を担う存在となっていくのではないでしょうか。
-今後Gunosyは、インターネット広告業界に対してどのようなポジションを担っていくのでしょうか?
コアテクノロジーの言語処理や機械学習を生かして何かできたら面白いなと思いますね。ここからは個人的な見解ですが、AIスピーカー等も、戦っていける余地があると思っています。ニュースを音声で読み上げるのではなく、スピーカーから集積できる会話を言語処理のテクノロジーで、どういう人物なのか、あるいは家庭なのか、というデータを収集するということは恐らくAmazonやGoogleも取り組んでいるはずで、仮に今後私たちがそういったAIスピーカーやそれに代わる何らかのデバイスを作ってもいいのではないか、みたいなことは考えています。私はトムクルーズ主演の映画「マイノリティ・リポート*4」が好きで、作品中に登場する近未来的な技術の中には、そう遠くない未来で実現できるものもあると本気で考えています。たとえば道を歩いていて、「これをお探しではないですか?」と自分にしか見えないAR*5で話かけられる、という新しい広告のかたちとか。それを実現させるためには何が足りないのか?と考えると、もちろんいくつか足りていないピースはまだありますけれど、メディアとしてあのような世界観に近づけたら面白いと思いますし、デバイスを作る側にになってもいいのではとも思います。
変わらないコアは「ユーザーに喜んでもらえるコンテンツwith広告」をつくること
-近藤さんが実現させていきたいことを教えてください
マネジメントの観点でいえば組織作りですね。Gunosyは「長時間ではなく長期間働ける会社」ということを掲げていますので、それをより強化して、より若い人が働いて成長できる環境にしていきたいです。巣立っていくのは仕方のないことですが、5~10年いて、ここにいて圧倒的に成長できたと実感してほしいです。今私のチームでは特に、マネジメント方針として、一挙手一投足を指示することはせず、入口出口のみの理想像を語るようにしています。状況説明をして、着地先だけ伝えるイメージです。全てを指示すると作業になってしまうので、頭を使ってどうすべきか考えてもらっています。正直こんなにもどっぷりと若手の育成に携わるとは思っていませんでしたが(笑)、若手の育成に自分の経験が寄与できるのであれば、そこは貢献していきたいですね。
あとはやはり新規の広告商品開発です。単に面白おかしく何かやりましょう!ではなく、業界のトレンドを取りこぼさないよう様々なことをキャッチアップしながら、クライアントニーズを解決でき、且つ収益性にも繋がる、比類なき広告商品を作っていきたいですね。僕は今回、前述したライブ動画コンテンツで、広告を一つの要素にした番組をつくるということに関与させてもらって、ユーザーのリアクションも非常にわかりやすく、きちんとしたリッチなコンテンツを作れたことがシンプルにすごく楽しかったんです。今後も、「ユーザーにもっと喜ばれるコンテンツ with広告」を作っていきたいですね。今後のキャリアの中で、これは変わらない私のコアだと思います。
以上で、近藤さんのインタビューは終了です。
Gunosyで一緒にインターネット広告の未来をつくっていきたい方、ぜひこちらからご応募ください!
*1:ユーザーの位置情報を元に広告を配信するアドテクノロジーの一つ
*2:定期所得
*3:
Gunosyでは全メンバーが、会社の重要な数値指標(KPI)が何であるか、その目標値と今日の数値を共有しています。誰かの経験や勘ではなく、数字や事実をベースに議論や提案ができること。それがGunosyで一緒に働くメンバーに求められる、もっとも重要なことです。
*4:作品中には「網膜認識により特定された個人にのみ表示される街頭広告」や「空間で手を動かすことで自在に操作できる映像ソフト」、「音声認識する家具」etcスティーブン・スピルバーグ監督が想像した、様々な現実味ある近未来技術が登場する
*5:拡張現実