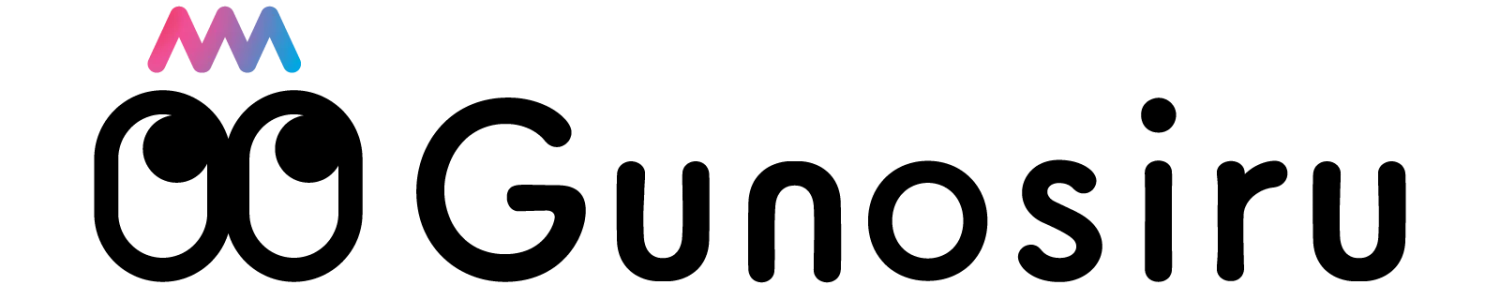こんにちは、採用広報の市村です。2018年9月から、代表の交代や子会社の設立、様々な体制変更などが行われ、Gunosyは新たな組織へ生まれ変わります。エンジニア組織としては、設立以来CTOとしてGunosyをけん引されてきた松本さんが退任し、新たにVPoT、VPoEが就任、技術戦略室も新設されました。そこで、今回のGunosiruでは、Gunosyエンジニア組織のこれまでとこれからのお話を、ご退任される松本さんと、新たにエンジニア組織をけん引されていく3名にお話を伺いしました。ぜひご覧ください。

小出さん(写真右)
外資系IT企業を経て、2014年Gunosy入社。入社後はインフラ構築の自動化やCI/CDの推進、プロダクト横断的にアーキテクトを担当。また、至近では「グノシー」、「ニュースパス」の記事配信ロジックの高度化なども担当。2018年9月、VPoT 兼 メディア事業部データ分析部長に就任。
松本さん(写真中央右)
東京大学在学中からアルバイトとしてGunosyへ入社し、約5年半CTOとしてエンジニア組織をけん引。iOSおよびAndroidにおける企画・デザイン・開発、Webサーバ開発、AWSインフラ構築、KPI整備、社内ツール整備、各種パフォーマンス向上など幅広く担当した。2018年8月末に退任。
吉田さん(写真中央左)
東京大学大学院工学系研究科修了。大学院在籍中に2012年当社を共同創業。2012年度IPA未踏スーパークリエータ。データ分析、アルゴリズム構築等を担当。2018年9月より執行役員技術戦略室室長兼広告事業本部副本部長。
加藤さん(写真左)
ソーシャルゲームの開発、アドテク企業でのデータエンジニアを経て2015年Gunosy入社。「ニュースパス」の立ち上げや広告配信ロジックプラットフォームなどを担当。また2017年からエンジニア採用の責任者としての役割も担う。2018年9月、VPoEに就任。
-約5年半CTOとしてエンジニア組織をけん引してきた松本さんですが、先月8月末をもってGunosyを退任されました。これまで、どのようなミッションで組織を率いてきたのでしょうか。
松本:この5年半、スクラムの導入や数値の見方、レポート作成の共通化や評価制度の工夫等、本当に幅広く色々と取り組んできましたが、一貫して注力してきたのは、課題解決型組織として成長させることだと思います。「職人」ではなく、実際にユーザーに価値を届けるために、「自ら課題発見、解決ができ、数値やファクトベースでプロダクト改善ができる」人材が中心となるエンジニア組織をつくろうと奔走してきました。さらにはその中で新技術も取り入れ、新しいテクノロジーを疎かにしないということも意識してきました。
-若手エンジニアの成長にも貢献されていたと思います。
松本:若手に対しては、挑戦してもらうということを大事にしてきました。成長するためには、場を踏むことが重要だと考えていて。僕自身、入社当初はAWSもわからないくらいの状態でしたが、ひたすら場を踏むことで今では様々なことができるようになりました。なので、できるだけ挑戦できる環境や、それを支えられるチーム構成等を考えて取り組んできたつもりです。新卒1年目のメンバーに、パーソナライズエンジンの開発を任せたこともありますし、色々な技術を試せる場をつくることができたことは良かったのではないかと思います。
-エンジニア組織だけでなく、全社へ与えた影響も大きかったのでは?
松本:そうですね。これまで、Gunosyという会社自体をエンジニアリングすることに尽力してきたと思っています。数字でのコミュニケーションを全社に浸透させたり、プロモーションチームにエンジニアを投入してテクノロジーを活用すべきワークフローを改善したり、セールスとも連携して様々なプロジェクトを推進したりと、テクノロジーをどう活用するべきか、実感してもらいながら取り組んできました。そのあたりは貢献できたのではと思います。
-設立からこれまで、紆余曲折あり良いことばかりではなかったと思いますが、現在のエンジニア組織は非常に健全な状態だと思います。何が最も重要な要因でしょうか。
松本:そうですね。上場前後や、方針転換時はやはり大変なことが多くあり、メンバーがGunosyを去ってしまったり、僕にとって試練の時期も当然ありました。様々な困難を乗り越え、いまのような素晴らしいチームに成長することができた理由は、当たり前ですが、「丁寧なコミュニケーション」にあると思います。たとえばサービス監視の輪番担当に対する手当や休暇の支給等、色々な制度を設けもしましたがそれは枝葉にすぎず、「メンバーの話を面と向かってちゃんと聞く」ということが根幹的に重要でした。なので、「聞いてあげられる人」をつくるためにマネージャー等のポジションを育成・新設したり、細かい「1on1」制度を整えたりしたことが、シンプルだけど最も大切なことだったと思います。そして、そんな風に全力で組織づくりに向き合えたのは、どんな状態でも冷静に、常にプロダクトを改善し続けていた吉田さんの存在があったからだと思います。

-では、今後組織はどう新しく変化するのでしょうか。まずは、新設された「技術戦略室」についてお聞かせください。
吉田:端的にいうと、これまでエンジニアは開発本部という組織に所属していましたが、この9月から全社的に事業部制に変わり、各エンジニアがそれぞれの事業部に所属するようになります。なので、各事業部のエンジニアメンバーがより事業に集中できるよう、エンジニア全体を支える組織づくりということをミッションとして「技術戦略室」は新設されました。新しくVP of Technology(技術責任者、以下VPoT)に小出さん、VP of Engineering(マネジメント責任者、以下VPoE)に加藤さんが就任しましたが、VPoTは技術のトップとして、事業部横断的な技術課題の解決や、サービス開発の安定性と効率性を向上させる開発基盤の共通化、新技術導入の推進が主なミッションです。一方VPoEは、ひとや組織に関するマネジメント全般を担います。

-VPoTに就任された小出さんは、具体的にどのようなことに注力していくのでしょうか。
小出:前提として、Gunosyはプロダクトをつくってユーザーに届けている会社で、僕らエンジニアがものをつくっているのは、ユーザーに価値を届けるため。その観点で、たとえば昨年リリースしたライブ動画やパーソナライズのような、新しい技術領域を取り入れながら、これまでとは別の価値をユーザーに届けるということが、一つVPoTとしてのミッションです。また、それそのものがユーザーにとっての価値に直結せずとも、リリースサイクルや開発スピードがより速くなることも間接的にユーザーへの価値になっていくと考えており、よりスピード感をあげていくために、開発やテスト、デプロイといった一連のワークフローを、新しい技術を取り込みつつ、改善していきたいと思っています。それはこれまでも重要視して取り組んできましたし、これからもそうしていきたいと考えています。なので、そのような2軸を意識して動いていこうと思います。
–加藤さんは、ご自身も生粋のエンジニアであったところから、昨年からエンジニア採用責任者として徐々にキャリア転換され、今回「ひとと組織のマネジメント」を一手に担う立場へ舵を切られました。大きな転換期であると思いますが。
加藤:そうですね。僕自身6年ほどエンジニアとして、Gunosyだけでなく色々なエンジニア組織をみてきて、「ひとや組織のマネジメント」という部分は、きっと得意でない人が多いのだろうなと感じてきました。もちろん僕もまだまだですが、人と人の間や、異なる文化をもつ組織の間にたってバランスをとったりまとめたりする役割は苦手ではなく、そういった立場で動いた方が組織の役に立つのではないかと考えました。今後は、エンジニアメンバーが困ったり、組織としての方向性を示さなければいけなくなったとき、僕と吉田さん、小出さんが中心となり、解決していかなければなりません。また、いま会社として総合インターネット企業という目指すべき姿があり、恐らくプロダクトや事業が増えていくことになると思います。それに伴って組織の規模も大きくなるはずで、我々だけで全てをマネジメントするのには限界が来るだろうと思いますが、そうなると各チームのマネージャー陣の動き方がとても重要です。基本的にチームの課題はチームで解決を目指すのが理想ですが、それでも解決しないときは僕らを頼ってほしいし、頼られる存在になりたいです。そのため、規模拡大してもスケールできる組織になるための準備を、今から色々と仕込んでいきたいと考えています。ハックするものがプログラムから人になった、というところでしょうか。僕の場合は。

-松本さんのご退任について、なぜこのタイミングだったのでしょうか。
松本:僕はこれまで、「自分をクビにできるくらいの優秀なチームをつくることを目標にしよう」と考えていました。2016年「ニュースパス」のリリース後しばらくは、新規事業の立上げや、方向性を示す、というところをぐいぐいけん引する人がまだ少なく、僕が担当してきました。しかし、アドのパーソナライズをスタートした頃くらいからそこが強化されてきて、今では「こうあるべき」と多くのメンバーが意見を主張し、僕が関わっていない様々なプロジェクトが立ち上がり、実際に成果を出し始めたりして、僕がいなくなっても問題のない、強いチームへ成長したと思えました。
さらには、子会社LayerXが立ち上がる等本当に新しい体制になろうとしている今、中途半端に踏み込み、影響を残すのは本意ではありません。僕のエッセンスを入れずに、新しい体制をつくっていくほうが、新組織にとって良いことであると捉えています。
また個人的なことを言えば、VRやAR、Fintech等、とにかくあらゆる技術に取り組んでみたいと考えていて、最近執筆した「xOpsと組織設計」という書籍の中でも書いた人間のプロダクティビティエンジニアリングといった部分等、個人的に追求したいこともたくさん出てきました。これらの様々な状況が重なり、このタイミングでの退任を決断しました。今後は自由な時間をもち、上述したようなことに挑戦しようと思っています。
-今後Gunosyとどのように関わっていくのでしょうか。
松本:これからは、GunosyやLayerXを、技術顧問というかたちで支援していきます。今後様々な新しい技術が登場してくると思いますが、そのときにGunosyが淘汰されないよう、情報のインプット等は引き続き都度していきます。また、ブランディングの方向性を一緒に考えたり、僕が繋がっているあらゆるコミュニティのキーパーソンを紹介して新たな事業推進の後押しができたらいいなとも思います。あとは採用の部分でいうと、Gusnoyを知ってもらうきっかけをつくる、テクニカルエバンジェリストのような役割を果たしていきたいと考えています。
–Gunosyエンジニア組織の今後は
吉田:ものすごいスピードでテクノロジーや世の中が変化していく中で、新しい技術的な視点で会社を変化させていくというところを、まずは積極的に取り組んでいきたいと考えていますね。
小出:先程も少し触れましたが、新しいプロダクトをより高速なスピードで生み出していける組織になれるよう、尽力していきたいですね。これまで、もちろん全てが上手くいった訳ではありませんが、新しいプロダクトを次々と立ち上げ、成長させてきました。今まで様々なプロダクトで試行錯誤し、エンジニアが苦労して手にしてきた知の集約を、新しいプロダクトの立ち上がり速度を上げるために活かしていきます。それと同時に、もっとメンバーを増やしていきたいです。どれだけ省力化しても、やはり人は足りない。人がいないとプロダクト改善していけないですから。その省力化の部分は僕が、採用については加藤さんがけん引していきます。
加藤:そうですね。採用の部分でいうと、これから新しい組織になるので、「これはひとつ、新しいチャンスだ」と思ってもらえる野心のある方にぜひきてほしいです。Gunosyは「グノシー」のテレビCMの印象が非常に強い会社だと思いますが、それ以外のことを、印象的なものとしてまだまだ露出できていないなと感じます。手前味噌になりますが魅力的な人や仕事がこんなに多いのに、伝え切れていません。そういったところを今後は余すことなくアピールしていかなければと思っています。
小出:新しいプロダクトをつくりたい、事業化していきたいと思っている人には非常に良い環境だと思います。Gunosyは一部上場して一区切りではなく、まだまだプロダクトが増えていくし、その数だけチャンスがあります。「そのチャンスをものにしたい」という、やる気の溢れる人と一緒に働きたいです。

加藤:前述の通り、これまで開発本部としてひと固まりであった組織が各事業部に分かれる体制に変化するので、「エンジニア組織」というかたちでない中で上手くまとめていく必要があります。そのために僕らは何をすべきか、より議論し実践していかなければなりません。紆余曲折を経て非常に良い状態にあるいまのエンジニア組織、それをまとめてきた松本さんから、僕らはその役割をバトンタッチされている。なので、今はメンバーにどれだけ自分たちができるのか?というのを見られている時期であると思いますし、その期待に応えていかなければいけません。僕らにタスキが渡されてよかったとメンバーに思ってもらえるように取り組んでいきたいです。
-最後に、松本さんにとって「Gunosy」とは
松本:最後にすごい質問きましたね(笑)。難しいですが、一言でいうと「最高のチーム」でしょうか。ありがたいことに色々な企業の方から、組織づくりについてご相談いただくことも多くありますが、こんなにすごいチームは中々ないと思っています。偶然ヒットする何かを生み出して、それを定量的に伸ばすことができている会社は正直少ないと思います。Gunosyは、もちろん全てが上手くいった訳ではないですが、「グノシー」に始まり様々なメディアをいくつもグロースさせ、広告事業や、ブロックチェーン等の新規事業も展開し、成長し続けている。今後も自分たちの強みを活かして、より盤石なチームに成長していくことを祈念しています。


今回のGunosiruはここまでです。
Gunosyは、新しい組織で貪欲に成長したい!という意欲的な方を募集しています。
少しでもご興味がある方は、ぜひ下記リンクからご応募ください。お待ちしています!