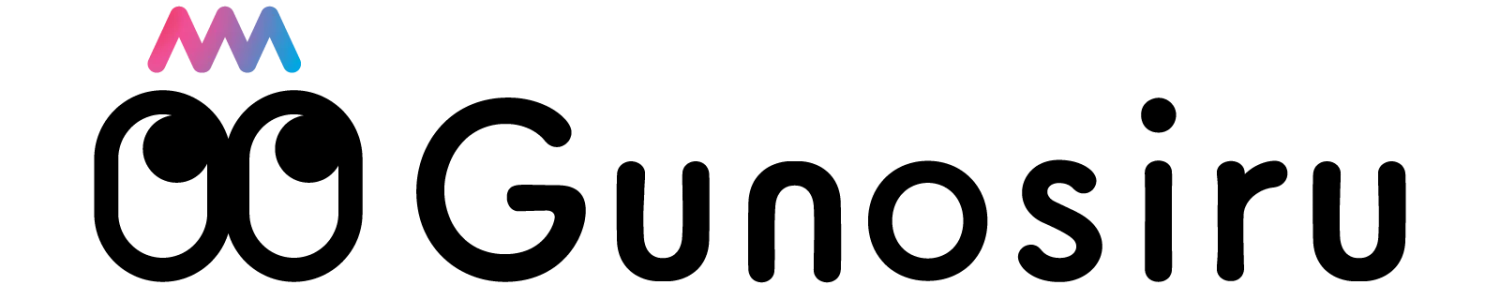創業以来、Gunosyのエンジニアは少数精鋭のスタイルを貫いてきました。それが独特の開発環境や風通しの良さにつながるのですが、実はもうひとつ、新卒社員にも入社当初より大きな裁量が与えられるという特徴があります。
今回は2022年入社の新卒エンジニア2名から入社後に取り組んだチャレンジングなプロジェクトやミッションについて語ってもらいました。
日下田さん(左)/Gunosy Tech Lab Media ML
2022年4月より新卒としてGunosyに入社。早稲田大学機械科学航空学科で機械工学や材料力学、流体力学などを学ぶ。その後大学院に進み機械学習に触れる。現在はGTLにてアプリの改善に力を注ぐ日々。趣味はゲームで現在はスプラトゥーン3にハマっている。
杉山さん(右)/メディア開発部 第二開発グループ
日本工学院八王子専門学校ITスペシャリスト科在学中の2022年2月よりインターンとしてGunosyにジョイン。4月から新卒としてメディア開発部に所属。管理画面の改善案件を中心に手掛けている。趣味はゲームと筋トレ。特に筋トレはここ数ヶ月ハマっている。
“やりたいこと”の先にGunosyがあった
ー学生時代はどんな勉強をされてましたか?
日下田:父親がダイカストの工業所を経営しており、跡を継ぐ可能性を考えて早稲田大学の基幹理工学部に進学しました。機械科学・航空学科という学科で主に物理的、機械的な分野を勉強していました。ただ、3年生の頃に自分が専門的に進む道は本当にこれでいいのか、と悩むようになりまして。
ちょうど父親も自分と似たことを考えていたようで、むしろ事業に直結しない分野を勉強してほしいと背中を押してくれた。それで大学4年の研究室配属あたりから機械学習に取り組みはじめたんです。
杉山:僕は4年制の専門学校だったのですが、この道を選んだきっかけは中学生の頃のプログラミング体験です。ただ、向いているのかどうかの自信がなく、高校は普通科へ。その後いよいよ進路を決める段階になって、やはり興味あるのはITの分野だと確信したんです。
学校では情報技術研究部というサークルに入っていて、ネットワーク周りについて特に力を入れて勉強していました。Wi-Fiなど通信インフラの「目に見えない部分」を理解できる楽しさに惹かれていたんですね。
ーGunosyを選んだ理由は?
日下田:自分にとって何が楽しいかを考えたとき、作ったものがユーザーに届き、ユーザーの生活が便利になったり喜ばれることだという結論に至りました。さらにそのフィードバックを直接もらえるとうれしい。Gunosyはメディアとしてユーザーに直接情報を届けているし、結果が数字であらわれるのでベストフィットでした。
杉山:もともとアプリを使っていたこともあって応募しました。選考インターンでは実際に働く環境や人、仕事内容に触れる機会が多く、理解が深まったのを覚えています。いま考えるとあの時に入社意思が固まりましたね。面接はほぼオンラインでしたが、話しやすい雰囲気をつくってもらえて非常に助かりました。
ーいまのお仕事について聞かせてください
杉山:2月からインターンとして勤務していたんですが、当時から業務は実戦そのもの。管理画面の機能改善を中心に、ほとんどいまの仕事と変わらないですね。目下取り組んでいるのもクーポン管理画面の一時保存機能について。クーポンを入稿する際にさまざまな項目を入力するのですが、これまで一時保存ができなかったんですよね。メディアさんから多くのご要望を受けて鋭意開発中です。
日下田:僕はグノシーアプリのタスクとして、新規ユーザー向けトピックタブの改善を手掛けています。新規ユーザーに定着していただくための記事クリック率がどうやらあまり高くないとのことで、より興味ある情報をレコメンドできるよう、現在のロジックをチューニングしているところ。日々改善を繰り返しています。
毎日がチャレンジの連続
ーいずれも重要なプロジェクトですね
日下田:本当によく任せてくれているな、と実感する日々です。僕は特に大学でプログラミングやアプリ開発をやってきたわけではないので、触れたことのない言語ばかり。GolangにしてもPythonにしても勉強するところからがスタートです。だから何かをやり遂げるたびに達成感が(笑)。
新卒でも実際にグノシーアプリに変更が加わるようなプロジェクトを任せていただけたり、そのプロジェクトも分析から実装内容の決定、そして自分でコードを書いて実装までまるごと手掛けられるので…おそらくこんな環境はなかなかないと思いますよ。
杉山:それは僕も感じています。インターンの時はさすがに定義されているタスクがメインでしたが、入社後はタスクの定義から任せてもらえる。たとえば一次保存機能がほしいと話をされたとき、どこまで実装するかという要件を決めるところからはじまるんです。この一連のフローは経験したことがなかったので、ものすごく実力がついたなと。
要望を要件に変えるのって難しいんですよね。そのためにはもっと質問力を上げなくてはなりません。ただ僕がSlack上で要望についてやりとりしている時、チームのみなさんがリアルタイムで追加質問を投げてくれて。周囲のサポートのおかげで新しい視点が芽生えました。
ー任せるといっても放置放任ではないと
杉山:そうなんです。ウチのチームだけじゃないと思いますけど、Slackのコミュニケーションも盛んですし、わからないことがあればmeetや朝会共有後に話しかけることができたり。リモート中心ではありますが雰囲気も面倒見もすごくいいと感じます。
日下田:Gunosy Tech Labも同じですね。Slackでのやりとりも柔らかくフランクでありながら、仕事は真面目でメリハリがある。聴きたいことや質問を投げるとあちこちから答えが返ってきます。得意分野だと自分のチーム以外の人からも声がかかったりして。温かい人ばかりですね。
ーこの半年で大きな成長実感を得られた
日下田:そうですね。最初にタスクをいただいた時は本当にできるのか…なんて思ったし、責任も重い。当然プレッシャーもあります。でももともとGunosyが一つのプロジェクトに関して分析から実装まで一手に任せてもらえると聞いていたし、その点を魅力に感じていたので。ゼネラリスト志向の僕には格好の成長ステージではないかと思います。
杉山:全体のフローをやることの良さとして、視野の広がりがあります。それまでの僕は技術だけに集中していたんですが、プロジェクトを通じてかなり視野が広がりました。その結果、オーダーに対して粛々と開発するだけではなく、こちらからさらなる改善提案や機能提案もできるようになりますからね。
経験不足は知識の蓄積で補う
ー働く環境はどうですか?
日下田:とにかく働きやすいですね。リモートも出社も選べるし、フレックスなのでコアタイムさえ守れば自由に働く時間を設定できます。
杉山:まったく同じですね。違いがあるとすればGunosy Tech Labに比べてウチのチームはリモート比率が高いというぐらいかな?
ーいまの仕事のやりがいはどうでしょう
日下田:やはり実際に自分が作ったプロダクトをリリースして実際どれぐらい使われるかが数字でわかる点ですね。ユーザーからのフィードバックを直接実感できるので入社前の思いが叶っています。数字はやっぱり正直ですから。
杉山:僕は管理画面中心なのですが、それでも社内の方に喜んでもらえているのを見ると手応えと実感が湧いてきますね。あと、タスクを得て知ることが増える点。今回はこれを新しく知ったとか、そういった知識の蓄積にもやりがいを感じます。
日下田:いままでは順調だったけど、これからシビアな局面での開発も増えてくると思うんですよね。壁にぶつかるだろうけど、それを超えて成長していきたい。
杉山:僕もいずれ選挙やスポーツなどのイベントを任されるようになると思うので、そこで自分の足りないところと向き合うことになりそうです。最大の課題は経験不足なんですけどね。
ー経験不足を埋めるにはどうすれば?
杉山:やっぱり経験がない分は知識で補うしかないので、日々勉強を欠かさないことですね。僕の場合はどういう質問をすればいいのか。そこから少しずつ広げて知識を獲得していく。
日下田:自分も全く経験のない状態でこの業界に入ってきているので、日々勉強しつつ実践の繰り返し。幸いなことに本当に優しい先輩方がGunosyにはたくさんいるので、とにかく頼りながら吸収するのが王道ですね。
ー最後に、将来のビジョンをお聞かせください
日下田:企画をやってみたいです。現時点ではユーザーのクリック率が悪いから改善してよ、という粒度で投げられるのですが、それを自分で施策から考える。より上流というか、プロジェクトオーナーですね。
そのために必要なのは人にものを伝える能力。Gunosy Prideにある『サイエンスで機会をつくる』を体現するためにも、きちんと科学的に根拠のある提案ができるようにならねば。ビジョンを叶えるための必達目標です。
杉山:僕はとにかくイベントをまるごと任されたい。いまはまだ機能だけなので、もっと上流から任されたいですね。そのためにはプロジェクト全般において知識を付ける必要があると認識しています。
いまGunosy Prideの話が出ましたが、僕が常に心がけているのは『三方よし』。たとえば管理画面の機能を作るとして、パブリッシャーのためだけでなく社内の利用者にもまなざしを向ける。コード一つとってもエンジニア目線で「いい」と感じられるものを作る。これはチーム全体でも目指しているテーマでもあるんですよ。
ーお二人ともありがとうございました!